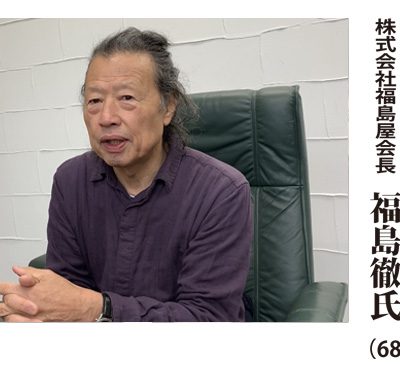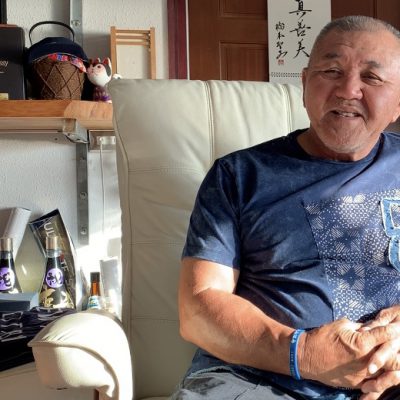東京・あきる野市に米山医院がある。院長の米山公啓氏は白皙長躯の開業医で、280冊超の著作がある人気作家だ。二刀流となった源流、ベストセラー作家のアイデアの源泉、認知症を予防したり脳をよみがえらせる方法などについて聞いた。
■ゲスト
作家・医学博士 米山公啓 氏
■インタビュアー
旅するライター 山ノ堀正道
北杜夫で医者の世界を知り
筒井康隆で作家志望となる
――こちらのクリニックにはどんな患者さんが見えるのですか?
米山 症状を問わず、幅広く受け付けていますが、慢性疾患や認知症、軽い鬱病などが多いですね。
――待合室にお父様の絵画とプロフィールが掛けられてありますが、お医者さんの家系ですか?

米山 祖父は甲府の南の上曽根町(現・甲府市)で歯科医を開業していました。
父は内科医だったが、肺結核を患い病気がちで開業医になれなくて、僕が小学校1年生のときに愛知県岡崎市の企業の診療所で産業医として就職しました。絵はセミプロ級です。
――先生が医師を目指したきっかけは?

米山 中学が比較的秀才が集まる学校だったので、1年生のときに北杜夫の本を読んで医者の世界を知って、海外旅行で世界中を回れていいなと思った。
その後、なだいなだ、斎藤茂太に続いて、若手純文学「第三の新人」の安岡章太郎を読んだ。
そのうち父親が体調がよくなり、僕が2年生のときに東京・西多摩の福生へ引っ越し、半年後にあきる野で開業した。
僕が入学した都立立川高校は、都立青山高校に続いて学園紛争が起こり、数か月登校できなくて、筒井康隆の本を読みあさった。この頃は作家志望でした。
印象的だったのは父親が開業して1年ぐらいたって、僕が「北杜夫が好きだ」と言ったら紀伊國屋書店新宿本店で「北杜夫を全冊買っていい」と言われてすべて揃えた。そのとき開業医は儲かるんだなと思った。
あとは広く芥川賞作家の本を読んだ。
大学入学後は、アメリカのレイ・ブラッドベリなどSF小説が多くなった。
――大学院では神経内科へ進むことになるのですね。
米山 僕がいた第二内科は循環器内科と神経内科と消化器内科に分かれていた。最初はメインの循環器内科に1年間いて、あるとき神経内科の助教授の依頼で学会でスピーカーとして登壇したのをきっかけに目をかけてもらい、大学院2年目に神経内科へ移った。
当時の高齢者医療の現場の多くは「患者を寝かせておくしかできない」と蔑まれているようなところがありました。
山奥の昔ながらの病院へ行くと、30人ほどの老人が手足を縛られた状態で寝ていました。ほとんど無意味に近い点滴をしているだけで、僕はこんなことやっていていいのかと医療の世界の閉塞感に大いに不満を抱いた。
その後、聖マリアンナ大学の初代神経精神科教授で「長谷川式認知症スケール」開発者の長谷川和夫先生の一番弟子で、「老人の専門医療を考える会」を組織して活動していた天本宏先生が設立された天本病院(東京都多摩市)で外勤医として多摩市の家庭を往診する経験を積んだ。
大学には19年間いた。医局に入って、神経内科の診療例を増やして下の連中の博士論文の指導をしたりした。
『ロックド・イン症候群』が
BSフジでテレビ化される
――初めて執筆されたのは大学在勤中ですね。
米山 ある看護雑誌に「お医者さんの本音」というエッセイを書いたところ、連載の話をもらったのが始まり。内容以上に、看護雑誌に医師が書くということに批判が集まった。
それから大学勤務時代に出した最初の本が体制批判のレッテルを貼られ、僕は健康管理部の助教授という窓際に追いやられた。
言いたいことが言えて、やりたいことがやれるというのが僕の人生の基本コンセプトで、医局にいて好きな研究ができるのであればそのままいたかもしれないけど、研究費について年間の計画を出してくれとか言われると、期の途中でこの機械を買いたいと思っても買えない。
それらのことで退職しようと思ったけど、出版社の社長から「やめちゃだめだ。みんなが陥れてくるのを楽しめ。やめさせられるまでいたらいい」と言われ留まった。
その頃、残業がないから本が書けてよかったけど、僕の研究室が盗聴され、たれ込みがあったり、ボケた母親を介護したりで大変だった。
当時、大学を退職しても医者の免許があれば経済的に困ることはないと思っていたが、「助教授」という肩書きで本が売れているのではないか、その肩書きが外れたとき果たしてどうなるのか、という心配もあった。
僕が書いた最初の医学ミステリー『ロックド・イン症候群』(幻冬舎文庫)は、長崎俊一監督がマイクをにぎり、真田広之主演でフジテレビ「神経内科医 匂坂俊介の事件カルテ・ロックドイン症候群」として放映されるはずがお蔵入りとなった。それがもし地上波で放映されていたら次回作も撮る予定だったので流行作家になったかもしれない。
――どうしてお蔵入りしたのですか?
米山 理由はわからない。製薬会社を悪者にしたからかもしれない。7年後の平成9年にフジBSで夜中に放映されたが、全く注目されないで終わった。
――医学ミステリーを書かれたきっかけは?

米山 すでに開業していた友人の病院の待合室が私の本しか置いていなくて、そこへある出版社の社長が来て、僕に「本を出しましょう。新しい視点でライトな医学ミステリーでいきましょう」と言ってくれた。
その出版社が前年度にベストセラーを出していて、「3冊同時進行でいこう」と言ったから3冊まとめて書き下ろした。ただしその3冊が同時に返本されるかもしれないというリスクもあって、ひと月おきに出した。
医学ミステリーはこれまで12、3冊出したけど、一番売れたのは『臓器提供者』(双葉文庫)――。臓器移植が日本で2例目の年でタイムリーでした。
いろんな好奇心が
アイデアの厳選だ
――続いて記憶の本を出されました。
米山 健康や病の医療問題はずっと書いていて、途中から記憶の本が売れ出した。まだ「認知症」という言葉が世に出ていなくて「もの忘れ」の視点で書いて10万部売れた。
医療エッセイ、医学ミステリー、脳活性・脳トレと、売れるほうへシフトして実績を出したから、出版社が声をかけてくれ、テレビのMCまで担当することになった。
そのうち出版不況になり、ここ4、5年は奈落の底で、本が売れていない。
それでもここ2、3年、ぬり絵の監修本がシリーズ合計13万部を超えた。
今年5月に『幸せ運ぶコーヒータイム』(径書房)を上梓した。コーヒーがネガティブデータばかりなので、それを覆そうと思い健康効果を中心に2週間で書き上げました。
――先生の作家としての原動力は何ですか?
米山 出身大学が私立の新設の聖マリアンナ医大という医者としての強烈な劣等感があり、それが書くエネルギーになった。それもずっと書いて280冊になって、もう劣等感はいいかとなった。
――アイディアの源泉は?
米山 いろんな好奇心じゃないかな? ほしいものは誰よりも早く手に入れる。
医局時代に60万円だったAppleIIはボーナスをそっくりそのまま出して秋葉原で買った。それを医局で使っていたら「遊んでいるのか?」と言われた。医学辞書がないのでJISコードを引いて作った。
パソコンがもう少し早く入ってきていたら研究でも使えた。むかし研究者はお金のことを考えちゃいけないと言われたけど、いまは企業からお金が取れるような研究が評価される時代になったので隔世の感がある。
iPhoneも日本でまだ発売されていないとき、アメリカで娘に買ってもらって送らせて、みんなに見せて自慢した。結局国内で使えないので送り返したけど。
すべてがおもしろいことを見つけて早くやっていくというのが僕のスタイルです。
――クルーズにもよく乗っておられるようですね。
米山 ある出版社の社長に、船上医学ミステリーを書きたいからクルーズに行きたいと頼んだら300万円出してくれて、大学退職後、すぐに世界一周の船に3分の2周ぐらい乗って、ミステリーでなくクルーズ業界のことをエッセイで書いた。
クルーズ雑誌の編集長からは「もっといい船に乗れ」と言われて、翌年から世界中の豪華客船に乗って雑誌を1冊作った。NHKのBSにも出演した。
脳を若返らせるためには
新しい体験をすることだ
――最近、高齢者の交通事故が多発していますが。
米山 75歳以上の高齢者ドライバーは、運転免許証の更新で認知機能検査と高齢者講習の受講が必須となった。認知機能検査でひっかかったら詳しく調べたり、問題があれば運転免許証を返上しないといけない。逆に言えばこの検査で早期の認知症を見つけることができる。
――高齢者が認知症を予防したり脳を若返らせるためには?
米山 新しい体験をすることです。いままで自分がやっていないことをやりなさいということです。それを積極的にやっていくにはよほど好奇心が強かったり、新しい情報が入ってくる環境が必要です。子や孫がやっていることを見て、自分もやってみようと思わない限り難しいですね。
僕も60歳をすぎてやりきった感があり、2年間ぐらいなにもしなかった。それじゃいけないと思って通信教育の大学へ入学したり、グランドピアノを買って独学でピアノを習い始めた。先生はiPadのアプリ。ピアノをちゃんと弾けているかどうかはiPadのアプリが音を聞き分け判定してくれる。ゲーム感覚だから続く。1年前と違う脳を使うようになった。
――ご両親の終末は対極だったそうですね。
米山 母親は肺炎になって病院に入れて9ヶ月間寝たきりの状態でした。父親はギリギリまで家で面倒を見て入院3日で亡くなった。父親には一切延命を行ないませんでした。
――延命治療にも一石を投じておられますね。
米山 最近、少し考え方が違ってきました。神経疾患は寝たきりになって食べられなくなると、胃瘻を作る場合があります。われわれ医師としては、寝たきりで先はないしむりやり胃瘻をして長生きさせるのは可哀想じゃないかという考え方でした。それが胃瘻が簡単になって管理もうまくいくようになると、元気になるひとも出てきた。
だから選択できることが重要です。医者が自分のこれまでの経験をもとに一方的に「無駄だからやめましょう」と言うのもおかしいし、家族もしっかりした信念がないと判断が難しい。ガイドラインを作ってきっちりやっていこうとしても、時代によって考え方も違ってくるという話です。
ハリウッド映画で
自作を映画化したい
――他種多様な経験がすべて肥やしになりますね。
米山 ある大学病院の教授の収賄事件を書いて編集ミスがあったので出版社と謝りに行ったら言葉でボコボコにされた。そのとき人間というのはここまで酷いことを言うんだと思って、そのまま小説の描写に使いました。作家業をしていたらすべてネタです。
怒られようが失敗しようが、もの書きとしてはすべて使えるわけです。脳にもストレス発散のためにも、そういったポジティブシンキングが効果的です。
――これまでは医者と作家の二刀流の、どちらが楽しかったですか?
米山 両方おもしろいし奥が深い。患者さんに好奇心を持つということは医者にとってとても重要です。
作家業だと、いろいろな有名人に会うチャンスがあります。雑誌で、横尾忠則さんと対談するチャンスがありました。横尾忠則さんは僕の世代からすると憧れです。そういう人と対談できるのは作家の特権です。
――今後の夢は?
米山 これからの夢は映画作りです。日本の映画はあまり興味がないので、ハリウッド映画で自分の原作を映像化したい。あるいはNetflix(アメリカの映像ストリーミング配信事業会社)のオリジナルドラマや映画ですね。
一時かすった時期もありました。ある俳優がハリウッドデビューするから原案を考えてくれと言われて出したらボツになった。
ただし、こういうことをやりたいと言っていたらいつかは現実化すると思っている。
――日本と外国のミステリーは違いますか?
米山 外国のほうが緻密だね。いま僕は小説を読んでいなくて、寝る前はほぼNetflixです。あのストーリーの突飛さといいおもしろさといいあり得ない。あれを見たら本を読んでいる場合じゃない。これからもNetflixを見て研究していきますよ。
プロフィール
米山公啓(よねやま・きみひろ)氏
1952年生まれ。作家・医学博士。専門は神経内科。1998年に聖マリアンナ医科大学内科助教授を退職。東京都あきる野市の米山医院で診療を続けながら作家活動を行なっている。著書は280冊を超える。主な著作には『もの忘れを90%防ぐ方法』(三笠書房)、監修した『脳がみるみる若返るぬり絵』(西東社)はシリーズ合計13万部を超えている。