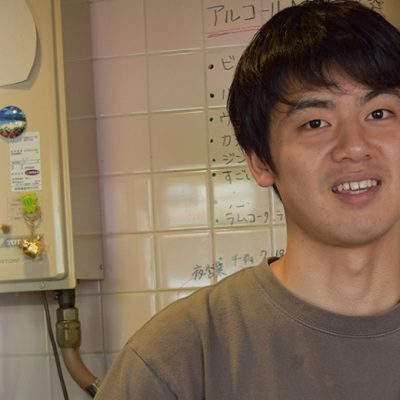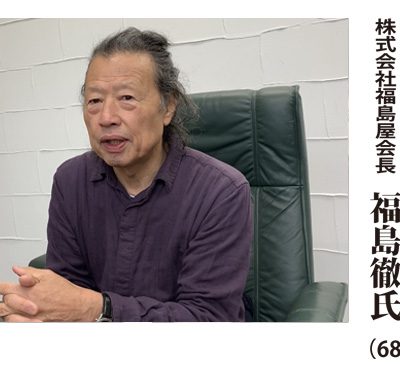弟夫婦の早朝の来訪
いつものように炊事・洗濯を行い、午後大学病院へ向かう。途中、千葉市あすみが丘(現・千葉市緑区あすみが丘)のシューベルトで、ショートケーキを購入。きょうは、次男の誕生日だ。
病院へ着くと、3階の売店で菓子を購入し、9階の病室を訪ねる。妻は沈んだ様子もなく、いたって明るい。というのも、きのう悪戦苦闘した点滴針をきょうは他の医師が1回で射れてくれたことがうれしくてしょうがないらしい。ショートケーキで次男の誕生日を祝う。
17時に担当の田川一真医師、板東真子医師、そして中村春博医師から患部の細胞検査の結果と、前日のMRI、本日のCTの検査結果の説明を受ける。専門用語が並び、わたしが口をあんぐと開いたままにしていると、田川医師が口火を切る。
「検査の結果、頭部や肺には影のようなものは見られず、現状では転移していない模様です。ただし念のため、リンパ節はすべて切除してしまうほうがいいでしょう。その手術は背中の皮膚移植とともに、今月28日に行いましょう」
途中で中村医師が割り込む。
「いえ9月の第1週になりました」
田川医師は担当でありながらそのことを事前に知らされていなかったため明らかに訝しげな表情に変わったので、わたしがあいだに入る。
「病院の都合もあるでしょうが、手遅れとならないためにも、一刻も早く手術を行なっていただきたいです」
中村医師と田川医師が順に語る。
「手術が一週間延びることは決定的なことではありません。むしろ、術後の経過や来週からの抗ガン剤投与の結果をみて、リンパ節の手術を行うのが有効だと思います」
「どちらも大きな違いはありません。ただし万が一リンパにガン細胞が隠れているとしたら、悔いを残さないために取ってしまったほうがいいでしょう」
わたしは話題を変えると、田川医師が答える。
「結果が良かったと言いながら、これから抗ガン剤投与やリンパ節の手術が控えています。現状と結果について、本人にもある程度説明してやらないと納得しないのではないでしょうか?」
「2年前、奥さんと同年齢の三児をもつ女性が同じようにできものが肥大し入院しました。旦那さんは非常にしっかりした方で医学的知識にも長けていて、いろいろ説明してあげたらしいのですが、ときどきわたしの言うことと食い違い、奥さんはどちらを信じていいのか迷ったそうです。そして、最後は残念なことになりました」
田川医師はそれでいつもわたしに最悪の話をしていたのかと合点がいくとともに、妻はともかく命が助かり良かったと思う。
わたしは早速病室へ戻り、妻に笑顔で語りかける。
「いま田川先生から聞いたけれど、結果は良好だそうだ。ただし、来週は予防の点滴を打つらしい。もうひと頑張りだからね」
「本当、よかった」
この朗報を早速、義母と母に知らせると、ふたりがとても喜ぶ。
その夜、9階の病室から市原市花火大会の花火が見えたらしい。病室の9人と翌日退院予定の横澤英子さんを呼んで見物を楽しんだといって、妻から電話がある。
今度は9時40分に弟からの電話だ。
「これから名古屋を出る」
「大網へ着いたら何時でもいいから電話をほしい」
早朝6時、町のサイレンとともに家のチャイムが鳴る。扉を開けると、弟が立っている。
「早いなー」
「3時30分に着いて車の中で夜を明かした」
「何だ、水くさい。鳴らせば出たのに」
彼はきょうだいの中で最も遠慮深い。義妹とメス猫も出てきて、一緒に荷物を部屋へ入れる。
ふたりにシャワーの説明や食材の位置などを教え、すぐに仮眠を勧め布団を敷いてやるが、義妹は朝食の支度と洗濯に取りかかり、てきぱきと動いてくれる。
そのうち次男が起きてきたので、4人で食事する。弟は冷蔵庫からワインを取り出して飲む。酒だけは遠慮がない。食後弟は床につき、義妹は後片付けを終えてシャワーを浴びる。
弟のみ14時に起きてくる。
「眠り姫のようだな。車の中で寝かせてやらなかったのか?」
「いくら寝ろと言っても寝んのよ」
「起こそうか?」
「いや、もう少し寝かせてあげよう」
わたしが焼き肉用の野菜をまな板でカットしていると義妹が起きてきて、みんなで遅い昼食をとる。
その日は弟夫婦に次男の面倒をみてもらい、わたしだけで妻を見舞う。
18〜19時まで、前日のメンバーに妻を交えたミーティングがあり、田川医師は平易にしかも患者を刺激しないような話し方で説明してくださる。お陰で妻は納得したようだ。しかし、病室に戻ると、腕がむくむのがどの程度か、また永久に続くのかを不安視する。
自宅で、そのことを弟に話すと「リンパ節を取ると抵抗力が無くなるんじゃないの? できることなら取らんほうがええじゃろう」と言う。
ついこの前まである程度死を覚悟していたので、リンパ節くらいどうでもいいくらいに考えていたが、ガンが再発した場合、今度こそ関所がなくなり、全身に及んでしまうのではという不安に襲われる。
妻の命が助かるのであればたとえ車椅子になってもと思っていたが、やはり人間は欲の塊で、次々に要求のハードルを高くする。自分もその例外ではない。
夜、寺本昭男編集長あてに妻の無事を知らせる手紙を綴る。