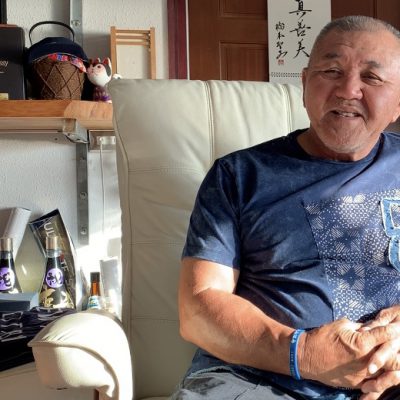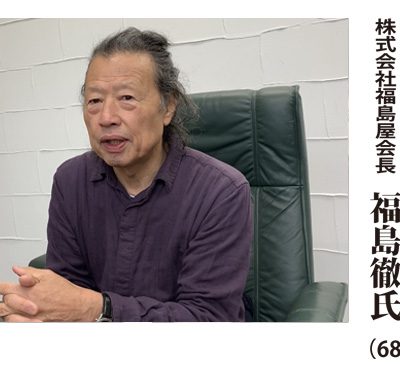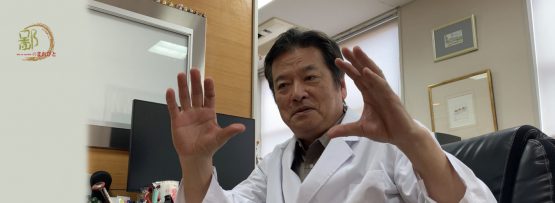次男誕生とワーカホリック
大網へ越して2年余りたち、妻が第三子を妊娠した。
夏季休暇を8月13、14日、17日の3日間とし、妻が希望通り15日に次男を産んでくれたので、会社へ連絡し、続けて「妻の出産休暇」を3日連続で取得。
平成2年のバブル崩壊以降、日本経済は徐々に失速。わたしの勤務先も営業所増設など数年で社員が倍増していたので、売上が増えても人件費が利益を大幅に圧縮していた。
親会社は、昭和62年に東京証券取引所第二部に株式上場し、第一部へ指定替え準備のため関連会社の経営改革にも着手。
わたしの勤務先も、ものづくりに特化し、販売を親会社へ移管し営業部門を大幅に縮小するリストラクチャリング(事業再構築)を実施。「深耕作戦」では、看板月刊誌が20万部から30万部に増えるなど収益も大幅改善。
そんなとき加藤佳寿夫専務(当時)からこう切り出された。
「きみはこれまで営業所長として売れない商品でも工夫して販売してくれた。うちの会社の月刊四誌のうちどれか一誌の現場責任者を任せたい」
「K誌を担当させてください」
「えっ、K誌は巻頭言と編集後記以外、ほとんど読まれていない雑誌だぞ」
「読まれていないので逆にやりがいがあります」
わたしにとって最初の編集会議には、その当時も社員2,000人超を抱える親会社の社長が初めて出席され、開口一番厳しいことばをかけられた。
「この雑誌は40,000部ほど発行している。現状ではコストパフォーマンスに合っていない。せめて会員から読まれる雑誌にしてほしい」
K誌は専門的な知識も要するため、編集長には税理士の寺本昭男常務(当時)が就かれていた。「会員から待ち望まれる雑誌」という命題を達成するためには、議事録中心からひとりでも多くの会員に登場してもらいファン化することだと考え、インタビューや座談会を多くした。
誌面刷新2年目に、親会社の社長から新たな提案があった。
「会員にだいぶ読まれるようになった。今後、『NHKスペシャル』のような記事がほしい。具体的には『文藝春秋』の〈日本国の研究〉(平成8年11月、12月号)の内容を広く知ってもらうために猪瀬直樹氏にインタビューしたらどうか? ただ、猪瀬氏が最初だと唐突な感じがするかもしれないので、これまで読者になじみのある政府税制調査会会長(当時)の加藤寛先生が適当と思う」
こうして平成9年1月号から寺本編集長のインタビューがスタート。1、2回は岩野清志取締役(当時)に取材補助と編集を担当してもらい、3回目からわたしが引き継いだ。
それ以降、さまざまなジャンルのオピニオンを探しご登場いただいたが、なかでもいちばん印象深いのは経済小説の大御所だ。腐敗した金融業界と再生を目指すビジネスマンを描いた著書が大ヒットし、その後映画化していた。
ご多忙のさなか、インタビューを快く引き受けてくださり、ご自宅兼仕事場を訪ね、1時間半たっぷりお話しをうかがった。
「ぼくはインタビューの謝金を受け取らない。お昼だから近所の旨い寿司屋で馳走しよう」
お言葉に甘えてメモをとる手を休めソニーの最新テレコに頼ってにぎりをつまむ。しかし会社に戻って愕然とする。寿司屋へ移動中、テレコのロックを失念したため、「戻る」「進む」ボタンがカバンの中で勝手に作動し、仕事場で聴いた話がほとんど上書きされていた。
メモと記憶を頼りにひとまず原稿に仕上げ、寺内編集長のチェックを仰いだ。
「先生はこうおっしゃったかな? ちょっと違う気がする。特に前半部分が弱いと思う」
「録音されていない部分がありメモを頼りに書きました」
「ぼくも記憶をもとに直してみたが、ご本人にチェックを仰いでほしい」
わたしは大御所の先生に「原稿をFAXさせていただきます」と言って送信すると、翌朝お叱りの電話をいただく。
「おいおい酷いじゃないか? ぼくが言った通りになぜ書いてくれない。随分はしょっている。それと接続詞はいらない。ぼくの原稿を載せるのはやめてほしい。ガチャン! ツー、ツー、ツー」
受話器を置いてもなお、汗が額からだらだらと落ちるのを感じた。
気持ちを鎮めて再度、ご自宅へ電話すると、ご夫人からこう諭される。
「主人はいま一所懸命、原稿にアカを入れているので安心してくださいね。あとでFAXを送ります。不明な点があればわたしが答えますから・・・・・・」
FAXを受け取ったが、追加・修正箇所があまりに多く字も細かいので読めない。
「これからすぐお邪魔させてください。大丈夫でしょうか?」
「わたしがいます。どうぞいらしてください」
一目散で電車に飛び乗りご自宅へ向かう。
「主人はこう言っていました。『彼は編集の経験がなくてデスクというじゃないか? ぼくもデスクや編集長の経験があるが、この仕事は中途半端な気持ちでできるものではない。彼には教えてくれる人間がいないだろうからぼくが厳しく指導してあげよう。彼の成長のためだから』と。主人のこと、悪く思わないでくださいね」
「ありがとうございます。先生によろしくお伝えください」
わたしは原稿を受け取ると、涙が出そうになるのを必死で抑え、最敬礼して辞した。
それからだ。「大御所の先生が見てくださっている。これまで以上に気合いを入れて、いい仕事をしなければ。テレコも常時2台用意しよう」と強烈な意欲が沸き上がった。
その後、仕事も楽しく徐々にワーカホリックになっていった。